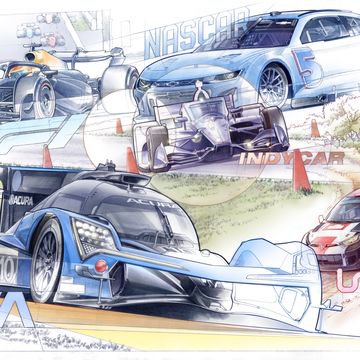第二次世界大戦後――。それは、イギリスにおいて自動車の価値が大きく変化した時代でもありました。戦前に持てはやされていた高級セダンの需要が大きく下落し、戦後復興に求められたのは頑丈で実用性に富んだクルマだったのです。高級車メーカーとしての伝統を持つローバーもまた、この時代の要請に応じることとなります。
ですがランドローバー(以下ローバー)には、確固たるビジョンがありました。そのビジョンとは文字通り、大地(Land)を駆ける(Rove)クルマの実現です。
「ランドローバー」の誕生とその歴史
1947年にローバーは、ウィリス・オーバーランド、アメリカン・バンタム、フォードによる共同生産の末アメリカで誕生した、「ウィリス」をベースとした1台の試作車を完成させます。
そのクルマこそ、「ランドローバー(シリーズI)」です。
プロトタイプで運転席は中央に配置され、。快適さなど微塵(みじん)も考慮されていませんでした。1948年に量産が開始される頃には運転席こそ従来型に戻されましたが、その他の点においてはプロトタイプそのままといった、まさに戦後の厳しい時代を象徴するクルマとして販売されることとなったのです。
初期の「ランドローバー」は、いわばクルマの姿をしたロバであり、ナンバープレートを取りつけただけのトラクターとも呼べる実に無骨なクルマでした。見てくれの良さなど微塵も感じさせないようなものでしたが、なんとそれが大ヒットを記録。英国陸軍が「ランドローバー」を輸送車として採用し、また戦後復興に伴う開拓や再開発に精を出す農家や労働者などからも、そのクルマの実用性が高く支持されたのです。
イギリス王室でも使用され、女王陛下を始めとする王族が地方へ赴く際の足として活躍しました。ローバーはそれから20年足らずの間に、鈍足でお世辞にも乗り心地が良いとは言えないこのクルマを、なんと50万台も生産することになったのです。
すっかり国民車として定着した「ランドローバー」でしたが、その飾り気のなさゆえでしょうか、誕生から40年以上が経過しても正式な名称が与えられていませんでした。目立ったモデルチェンジのあるごとにローバーが行ったのは、バージョンが更新されたことを示す大文字の「I」を付け加えるというものでした。シリーズI、シリーズII…といった具合です。
後においては「ミニ」がそうであったように、「ランドローバー」はまさにイギリスらしさを体現する象徴的存在となりました。そして象徴化された多くのクルマ同様に、「ランドローバー」もまた実用的なクルマから、ステータスシンボルへとその立ち位置を変えていくことになっていきます。
1990年に「ディフェンダー」と名を改めてからは、特にカルト的な人気を博すことになります。少し前までは、このような無骨なクルマに乗ろうなどとは思いもしなかったような人々までもが、「ディフェンダー」で街へと繰り出すようになったのです。
人気の高まりに連れて、当時の製造元であったローバーグループは裕福な購買層の好みに応じて、少しずつその持ち味を変えていくことになりました。インテリアはより洗練され、エンジンはパワーを増し、オフロードよりもオンロードでの走行を重視したトリムレベルが普及するようになりました。
少し過剰な特別仕様車が試されるようになり、現代的なアップデートも行われ、カラーリングも派手さを増していった時代の「ランドローバー」に、古い白黒映画を無理やり着色したかのような微妙な違和感を醸していたと感じているのは私だけではないかもしれません…。
ですが、そのような流れの中であっても、「ディフェンダー」が基本的特徴としての「頑丈さ」を失うことは決してありませんでした。ただしアメリカ市場においては、やや場当たり的な展開となったため、上手に物語を紡ぐことができたとはお世辞にも言えませんでした。
2020年、「ディフェンダー」がモデルチェンジ
そして今、私は2020年にモデルチェンジした新型「ディフェンダー」に乗り込んでいます。これからこのクルマを駆って、メイン州の深い森の中へテストドライブへと向かう予定です。そのレポートは後編でお伝えすることとして、まずはその前にもう少しだけこのクルマについて語らせていただくことにします。
もしこの「ディフェンダー」が、“大地に立つ機会を与えられないまま懐古主義にまみれた自動車ジャーナリストらにダメ出しされかねない状況に立たされた”新人選手であったとするならば、彼らの顔面に一発ぶちかましてやりたいという衝動に思わず駆られたとしても、誰も私を責めることなどできやしないでしょう。
見事に生まれ変わったこの「ディフェンダー」は、オリジナルが誇る不朽のデザインを踏襲するような顔をしながらも、まるで兵士の如き頑丈な臀部(でんぶ)を誇り、上官の目を奪うほどの繊細なウエストラインを無邪気に見せつけているのです。
この際ですので、もっと正直に申し上げておきましょう。
皆さんご存知の通り、過去のヒット作の劣化版コピーを生み出し続けるメーカーがあるのも事実です。しかし、レトロをうたうデザインなど、ただの“逃げ”に過ぎない…と私は思うのです。学生寮の壁に掛けられたゴッホのレプリカ程度のオリジナリティ、委員会による協議の末にあらゆる斬新さが却下されて、個性を奪われることとなる理想形のなれの果てと言っていいでしょう。
ランドローバーのデザインディレクターであるジェリー・マクガバン氏は、ロンドンのモダンな空気を身にまとい、組織の影響力を盾に持ち、また、それに見合うデザイナーとしてのエゴを備えた人物であることは疑うべくもありません。
だからといって、迂闊(うかつ)に我を見失うような愚か者でもありません。マクガバン氏がコピーマシンの「ディフェンダー」と書かれたボタンを押して、出てきたものに自らの署名を加えただけだなどと考える人がいるのであれば、それはマクガバンという人間をご存知ないという他ないでしょう。
最新型「ディフェンダー」の驚きのスペック
ここアメリカにおいても、「ディフェンダー」は道路を走る1台のクルマというよりも、鋼をまとった“野生児”として神話化された存在となりつつあります。
現在、ジープ「ラングラー」はアメリカで年間20万人もの購買者を魅了し、かつてない栄華を誇っています。それに対して「ディフェンダー」は、1990年代のピークを経た後、今では新車を求めるアメリカ人の数は年間7000人にも満たないのです。
このような状況を顧みるに、「ディフェンダーも、ついに過去の輝かしい歴史との決別を余儀なくされることになった」、と言えるのではないでしょうか。誕生時から採用してきたライブアクスルに別れを告げ、独立懸架式サスペンションを取り入れたことも、その表れと言えるはずです。
ピカピカの新車「ディフェンダー」で、荒野に乗り出して泥まみれになるのはもちろんアリですが、現代におけるSUVの主戦場はもはやオフロードだけではありません。公道においても新型「ディフェンダー」のアルミニウム製モノコックボディが、「110モデル」に標準装備されたエアスプリングが、395馬力の3.0リッター直列6気筒エンジンが、過当競争状態の続くSUV市場で独自の存在感を示すでしょう。
そして、ターボチャージャーに加え、電子制御のスーパーチャージャーによる「デュアルフォース・インダクション」、48ボルトのマイルドハイブリッドシステムによって、回転数2000rpmで約550Nmという豊かなトルクが引き出されます。時速0~100キロ加速は約5.2秒。時速240キロを誇る最高速度にも驚きの一言です(編集注:日本未発売のV8モデルの数値となります)。
ジープ「ラングラー」やメルセデス・ベンツ「Gクラス」を凌駕(りょうが)しようかという、洗練されたハンドリングも特筆すべきポイントです。その魅力は、走れば走るほどにハスキーな音色を奏でるエンジン音と共に高まります。4WDに特化したクルマで、ここまで見事にコーナーを駆け抜けることができるのは驚異的としか言えません。牽引能力はジープ「ラングラー・アンリミテッド ルビコン」の最大3500ポンド(約1600キログラム)とは比べ物にならない8201ポンド(約3700キログラム)を誇ります。
ランドローバーによれば、アルミニウムを多用したユニボディは一般的なボディ・オン・フレームの構造と比べて、3倍もの剛性を備えるとのことです。2ドアの2022年モデルの「ディフェンダー90」(296馬力の4気筒ターボ仕様車)であれば、オプション満載のジープやフォードよりもここアメリカでは手頃な価格設定となっています。4ドアで395馬力を誇る「ディフェンダー110SE」の場合は6万6450ドル(約759万円)から入手できます。これはメルセデス「G550」の半額程度に過ぎないのです。
中には、「雨道や未舗装の道を走らせるには抵抗がある」というオーナーもいるかもしれません。ですが、「ディフェンダー」の切り札と言えば、その無敵のオフロード性能であることは偽りのない事実です。切り替え可能なテレインレスポンスシステムや、2速トランスファーケース、センターデフロック(編集注:センターデフにおける前後輪の差動回転を止める装置のこと)や電子制御リアロッカーなど、充実の機能には目を見張るばかりです。
またフルリフト時には、11.5インチ(約30 cm)のグラウンドクリアランス(編集注:最低地上高。自動車の下面と地面とのすき間のこと)に35.4インチ(約90cm)の水深センサーを備えたオールラウンドプレーヤーとしての実力は、ジープ「ラングラー・ルビコン」の最高クラスの仕様車と匹敵するレベルです。
それでは私はこれから、「ディフェンダー」と共に1泊2日の旅へと向かいます。その過酷なトレイルを走破するレビューは、後編[完全なる生まれ変わりを遂げた新型「ディフェンダー」―深い森が支配するトレイルを走破した記録―]でお届けします。
Source / Road & Track
Translation / Kazuki Kimura
※この翻訳は抄訳です。